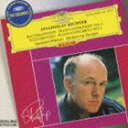弾(はじ)けるような感情と、
憐(あわ)れみ深いあたたかさ、
たくさんの変化が楽しめる名曲ですね。
- 【解説】チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番
- 【各楽章を解説】チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」
- 【5枚の名盤を紹介】チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番
- 【解説と名盤、まとめ】チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番
【解説】チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番
ロシアの作曲家チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第1番」は、「さみしさ」や「つらさ」や「やるせなさ」の要素を含みます。
けれども、そこから一転!
「ズバッ!!」と抜けるような明るさを放つ展開をする魅力的な曲ですね。
こんな解説があります。
さて、万人の心をゆり動かすこの名曲も、出来立ての頃はそういかなかった。献呈しようとした相手の先輩大ピアニスト、ニコライ・ルビンシュタイン(ルービンシテインとも)からは、演奏不能だとか、人真似が多過ぎるとか、こっぴどくやっつけられた。(中略)傷心のチャイコフスキーは、溺れる者の心で、面識もないままに、ハンス・フォン・ビューローに献呈したところが大いに気に入られ、ビューローのソロでアメリカで初演、大成功した。後に、ニコライも反省して作曲者に詫びを入れて、自らも演奏するようになったという。
出典:諸井誠 著 「ピアノ名曲名盤100」p196より引用
引用にありますルービンシテインのキビシイ言葉ですが、こんな言葉もチャイコフスキーに投げかけています。
「安っぽく、けばけばしいだけ。」
「陳腐で不細工であり、役に立たない代物(しろもの)。」
「貧弱な作品で演奏不可能 。」
ですって…。
気持ち、落ちますよね〜。
あまりにも、ヒドイ表現をされてますものね。
チャイコフスキーの気持ちは「激落ち」状態だったことでしょう…。
ただ、ルービンシテインは、チャイコフスキーの親友でもあったので、「悪意」のみで発した言葉ではないと思います。
「あまりにも素晴らしい功績をあげた者」に対しては、人って、けっこう嫉妬してしまうものですよね。
もしたしたら、ルービンシテインも「あまりの素晴らしさに嫉妬しちゃってた」なんてことはないのかな?
なんて…アルパカは想像しちゃうのですよね。
人間がデキていないアルパカも、実は、素晴らしい結果を出している人を羨(うらや)んだり、嫉妬したりして、苦しんだりしますね。
反省…。
ちょっと、脱線しました…💦
解説にもあったとおり、
- はじめ、チャイコフスキーはこの「ピアノ協奏曲第1番」をルービンシテインに献呈(贈物に)するつもりでいました。
- けれども、この一件があったため、気が変わり、ピアニストであり、また指揮者でもあった、ハンス・フォン・ビューローに献呈しました。
- けれども、この後、ルービンシテインは、チャイコフスキーに、お詫びをし、反省の気持ちを伝えます。
その後、ルービンシテインは、チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番を積極的に演奏して、広めてくれたようですね。
やっぱり、ルービンシテイン、いいヤツです。。。
↓チャイコフスキーとの友情についてはこちらをお読みください
【各楽章を解説】チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」
なんとも優美で、深い憂いをも秘めた名曲。
「これぞロシア音楽♫」という、独特の透明感を持った語り口の、チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番。
日々、「憂(うれ)いたっぷり」に仕事をするサラリーマンにも、けっこう共感を呼ぶのでは…。
まあ、少なくともアルパカはビンビンに共感する毎日です。ハイ…💦
それでは、各楽章について解説したいと思います。
この曲は第1楽章から第3楽章までの3曲で成り立っています。
第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ・エ・モルト・マエストーソ―アレグロ・コン・スピリート(速く、しかしあまり速すぎないように、堂々と、そして、活き活きと)」
華々(はなばな)しく、絢爛豪華で、親しみやすく、また、誰もが一度は聴いたことのある、有名なメロディで始まります。
力強いピアノの主張と、オーケストラが、それを支えながらも、チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」のテーマを勇壮に歌います。
さらにピアノがテーマを歌い、音の色彩が豊かに、音楽は展開します。
その後、まもなくして、音楽は一転して、ロシア的な憂愁(哀しみ、憂うこと)のメロディが展開します。
さまざまな音のグラデーションを表現し展開しながら、クライマックスに向かいます。そして、そのクライマックの瞬間はパッと明るく曲調がもどり、感動的に終わっていきます。
第2楽章「アンダンティーノ・センプリチェ - プレスティッシモ - クアジ・アンダンテ(歩く速さよりやや速く、素朴にー出来るだけ速くー歩く速さで(少し速め)」
なんとも優しく、そして、やわらかく、包み込むような調和された音空間が広がります。
そのメロディのイメージは淡い系のさくら色。
チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」の中の、静かで、癒やされる、憩い(いこい)の時間が展開しますね。

第3楽章「アレグロ・コン・フォーコ(火のように活き活きと)」
第2楽章の静けさとは、打って変わってのパンチの効いた1曲。
ウクライナに、昔からある民謡を、基調にした第1主題からして、ノリがいい。
すこぶるスピードが速く、快活で、その躍動感がハンパない。
また、音の連なりも、エレガントな響きをたたえていて、全くもって飽きさせません。
第2主題では優美な旋律をあらわします。
しかし、最後は再び、快活な音楽に戻りつつ、壮大なクライマックスを迎えます。

【5枚の名盤を紹介】チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番
「心が寒い。もう、折れそうだわ。」
独りで残業中の会社は、節電のため、蛍光灯の光が数本の暗〜い空間…。
「あともう少し踏ん張って、チャイコフスキー『ピアノ協奏曲第1番』を聴いて、心を取り戻しながら帰ろうか…!」
そんな時に、聴きたい名盤を解説です。
スヴァトスラフ・リヒテル:ピアノ
ヘルベルト・フォン・カラヤン:指揮 ウィーン交響楽団
「20世紀最大のピアニスト」とは、よく聞く言葉ですし、そう呼ばれるピアニストは多いです。
ところで、「最大」って、ひとりであるハズでは…。
なんて、考えると夜も眠れなくなるので、ここでは考えないこととして、その「20世紀最大のピアニスト」と呼ばれるひとりであることは、間違いないリヒテル。
ヴィルトゥオーゾ(圧倒的技巧)と、華麗で豪華でありながら、漂(ただよ)いくる「気品」。
それは第2楽章でも、いかんなく発揮されます。
録音が古いことが難点ですが、巨匠カラヤンとの演奏で、しかも、珍しくウィーン交響楽団を指揮した録音というアルバムです。
長い間、「名盤」のほまれ高い1枚。一度は聴いておきたいですね♫
マルタ・アルゲリッチ:ピアノ:キリル・コンドラシン:指揮 バイエルン放送交響楽団
「みずみずしいインスピレーションとタッチの織りなす感性のキラメキ!」が全編に満ちています。
女性とは思えないほど力強い第1楽章。
女性としてのやわらかさを発揮した、たおやかな第2楽章。
そして、第3楽章のピアノの「超高速での、情熱的な爆発」は、アルゲリッチの独断場!
愉快!
痛快!!
豪快!!
爽快!!!
そんな第3楽章を満喫したいあなたなら、コレっすよ〜♫
イーヴォ・ポゴレリチ:ピアノ クラウディオ・アバド:指揮 ロンドン交響楽団
第1楽章の「強い主張」の部分、「憂い」の響きはもちろんのこと、細部にいたるまで、その繊細さが失われることがありません。
第2楽章の安らぎの音楽も、その「繊細さ」のなせる表現の美しさには舌を巻きます。
そうであるがゆえに第3楽章のアップテンポで力強い曲の印象も強く残りますね。
全体的に、「チャイコフスキーの『憂いの美』があますところなく表現されている」1枚です。
アンドラー・シフ:ピアノ:指揮 シカゴ交響楽団
オーケストラのキレの良さがフレッシュですし、その背景のなかでのシフのピアノがまた粒(つぶ)だったきれいな音の輝きを発します。
シフのピアノが語れば、オーケストラの楽器たちが応え、その楽器たちが問えば、ピアノは雄弁に物語ります。
そして、たくさんの個性ある主張をまとめ上げる、指揮者ショルティはスゴイ。
とても、まとまりのある整った演奏です。
でも、そうであるがゆえに、主役(ピアノ)と脇役(オーケストラ)の役割分担がハッキリした演奏を好む方には向かないかも…です(汗)
ピアノの「徹底的主張」というよりは、「楽器たちとの愉(たの)しい対話」を楽しむにはいいかも…。
アルトゥール・ルービンシュタイン:ピアノ
エーリッヒ・ラインスドルフ:指揮 ボストン交響楽団
風格といぶし銀。
「熱くて過激な表現」とは、それが表面に出るか、内面からにじみ出るかの違いがあります。
前者の典型がアルゲリッチであるならば、後者はルービンシュタインですね。
とても安定した、あるいは安心感のある演奏ですね。
つまり、「はやる気持ちで、つんのめる感」がないのがいい。
目を閉じて、チャイコフスキーが、天の一角から降ろした音世界が本来、どんなカタチをしていたか、どんな安らぎの光を宿していたのかを教えてくれる。
そんな、粋(いき)な部分と、構築のがっちりした安定感のある演奏が聴けますね。
リヒテルとともに、ルービンシュタインも「20世紀最大のピアニスト」と言われることがあります。
これも「名盤」と呼ぶにふさわしいのではないでしょうか。

【解説と名盤、まとめ】チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番
さて、チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番、名盤の紹介と、解説はいかがでしたか?
「仕事をはじめ、なにかと、もの憂(う)いことが多いな…。」
そんな時は、いっそ憂(うれ)いの中にも、華やかさを秘めたチャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」を聴いて心を整えるという方法もアリかも…。
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事↓ (ここに、関連性の高い記事のリンクを貼る)