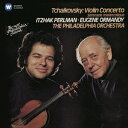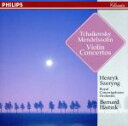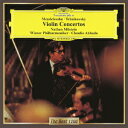あせる気持ちと、もの憂(う)さが交じる毎日の中、ひとにぎりの希望とともに歩もうよ。
- 【楽曲解説】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
- 【各楽章を解説】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
- 【5枚の名盤を解説】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
- 【解説と名盤、まとめ】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
【楽曲解説】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲は「憂いを秘めた豪華さ」を感じるなんとも不思議な魅力のある1曲です。
こんな解説を見つけました。
チャイコフスキーほど初演につまずきのあった人も少ない。(中略)この曲(チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲)など、今日傑作として知られている彼の作品の初演の時の評判はさっぱりだったのである。彼はそれだけ、その当時の聴衆の感覚よりも、50年先、100年先を先取りした作曲家だったといえよう。
この曲は、(中略)民族的な情感こそが、この曲の最大の魅力なのである。ことに、カンツォネッタ(小さい歌)と題された第2楽章にただようスラブ的憂愁の美しさは、比類がない 。出典:志鳥栄八郎 著 「不滅の名曲はこのCDで」p216より引用
「ヴァイオリン協奏曲」と言えば、ベートーヴェンと、メンデルスゾーン、それからブラームスの3人が作曲したものを「三大ヴァイオリン協奏曲」と解説されることが多いですね。
さらに、このチャイコフスキーが作曲した「ヴァイオリン協奏曲」を加えて、「四大ヴァイオリン協奏曲」と解説されることもあります。
それだけに、現在では名盤と言われるアルバムも多いです。
そんな名曲がチャイコフスキーの作曲当時は、えらく評判が悪かったことを知ると驚きですよね。
当時、ライプツィヒ音楽院の教授をつとめる、ヴァイオリニスト、アドルフ・ブロドスキがウィーンにおいて初演(作曲後、初めて演奏されること)を行います。
しかし、解説にあるように、ウィーンでの初演では、ロシア音楽に対する感心が薄かったこともあって、不評だったようです。
(事実上の初演は、ニューヨークにおいてレオポルド・ダムロッシュのヴァイオリン演奏によるものだったという説もあります。)
しかし、このアドルフ・ブロドスキは、この曲に愛情を感じて、その後も各地で演奏をくり返します。
そうすることで、だんだんと理解者が増えていったようですね。
いくら不評でも「本当にいい曲」ならば、いずれは多くの人に認められるものなのですね。

【各楽章を解説】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
それでは、各楽章について解説したいと思います。
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲は第1楽章から第3楽章までの3曲で成り立っています。
第1楽章「アレグロ・モデラート − モデラート・アッサイ(ほどよく速く、中くらいの速さで)」
まさしく、「憂いを秘めた豪華さ」がある珠玉のきらめきを感じる1曲ですね。
全体としては明るくて、豪華な印象の曲です。
でも、ところどころに、チャイコフスキー節(ぶし)と言いますか、憂いを秘めています。
また、情感をこめた寂しさも顔をのぞかせます。
でも、そうでありながらも、つややかな美しさが表現されています。
チャイコフスキーの、いかにもチャイコフスキーらしい彩りに満ちた1曲ですね♬
第2楽章「カンツォネッタ アンダンテ(情感をこめて、歩く速さで)」
第1楽章に見え隠れしていた「憂い」が全面に表れてくる楽章です。
さみしさや、悲しさに覆われたときには、こんな情感に、心が覆われますよね。
一面、純白に透きとおる雪の街に立ちすくんでいるような、そんな情景ともとれます。

第3楽章「アレグロ・ヴィヴァチッシモ(速く、はつらつと快活に)」
「今までの深い憂いはどこへやら…」
そんな疑問を持ってしまいそうなくらいの、
「晴れわたる、抜けるような、青空の輝き!」
そんな感想がピッタリの底抜けに明るい1曲ですね。
今までのさみしさ、悲しさ、つらさなどはこの時のための助走だったとも言えそうな元気で爽快な1曲です♬
【5枚の名盤を解説】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
イツァーク・パールマン:ヴァイオリン
ユージン・オーマンディ:指揮 フィラデルフィア管弦楽団
ある晴れた昼下がり、お堀のほとりにあるオープンカフェでコーヒーを飲みながら、スマホをのんびり眺めていました。
そこで、この「イツァーク・パールマン:ヴァイオリン」と「ユージン・オーマンディ:指揮」の演奏が、youtubeにアップされていることに気づいて、何となく聴き始めてビックリ!
オーマンディの、ガッチリとした重厚な音世界の中に響く、イツァーク・パールマンのつややかで、磨き抜かれた透明感のあるヴァイオリンの響き♬
聴き終わってコーヒーも飲み終わり、駆け込んだのはCDショップ。
家で聴きなおして、再び感動の嵐だったことは言うまでもないことですね。
アルパカにとってはそんな感動の思い出のある名盤なのですね♬
ヘンリック・シェリング:ヴァイオリン
ベルナルト・ハイティンク:指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲は、情感を込めて「美」を最高度に表現しよう。
そんな、熱い想いを肉体的にも、精神的にもギリギリまでしぼり出す感覚で演奏する素晴らしいアルバムが多いです。
しかし、この「ヘンリック・シェリング:ヴァイオリン」のアルバムは少し熱い想いを抑えながらチャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」に、本来ひそむ凛(りん)とした品の良さを存分に表現し尽くした名盤ですね。
この品の良さはヘンリック・シェリングの奏でるヴァイオリンならではのもの♬
ぜひ一度、ジックリ堪能(たんのう)して欲しい1枚です。
ナタン・ミルシテイン:ヴァイオリン
クラウディオ・アバド:指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ミルシテインの「美感」と「粋(いき)」のきいたヴァイオリンの語り口に、ただただ酔わされる魔法のにかかったような陶酔感ですね。
クラッ!!!<
あまりにうますぎて、近づきがたさまで感じてしまうのはバックのアバドとウィーンフィル演奏の美しさにもあるのでしょうね。
どこか「完璧過ぎる冷たさ」しまうのはバックのアバドとウィーンフィル演奏の美しさにもあるのでしょうね。
どこか「完璧過ぎる冷たさ」は感じるものの超絶技巧の陶酔を味わいたい方ならいいかもですね…。
ヤッシャ・ハイフェッツ:ヴァイオリン
フリッツ・ライナー:指揮 シカゴ交響楽団
ヴィルトゥオーゾ(達人、超一流)と言われたハイフェッツの名人芸が聴ける1枚。
「華麗!」「豪勢!!」「カッコいい!!!」
ありとあらゆる積極的な形容詞が冠される名盤。
ミルシテインの「繊細な美」とハイフェッツの「華麗な美」を聴き比べるのも一興ですよね。
選択に迷ったら、「繊細」か、「華麗」かで選んでいただければよろしいかと思います。
ハイ。。。
アイザック・スターン:ヴァイオリン
ユージン・オーマンデイ:指揮 フィラデルフィア管弦楽団
あらゆる面で、中庸をいく安心して聴ける心地いい1枚。
オーマンディの骨太でしっかり支えられたオーケストラのもと、磨かれ抜かれた美感で歌うスターンのヴァイオリンが心にしみます。
一度は聴いておいて、これをデフォルト(標準)として様々な演奏の個性の乱舞を楽しむなんていいかもですね。
多くのアルバムを聴きすぎて疲れたときに戻って来たい。
そんな篤実で誠実なイメージの素晴らしいチャイコフスキーですよね〜♫
【解説と名盤、まとめ】チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲
さて、チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲、名盤の紹介と解説はいかがでしたか?
現代人は「時間がない」と焦ることが多いですね。
それは、日々の中での、他人からの評価が低いことが原因かもしれません。
要は、なかなか承認欲求が満たされないことのいらだちからの焦りかもしれません…。
少し焦って、つんのめりがちな毎日にブレーキをかけながら、心を明るいほうへむけるのは、大事なことかもしれませんね。
そんな時、チャイコフスキーのさみしさと、それを突き抜ける明るさがギュギュッと詰まった珠玉の協奏曲で、気分転換なんていかがですか〜♬
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
↓こんな協奏曲も心にしみます。