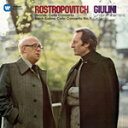若き日の思いがよみがえる
淡い回想、深まる音楽
心、癒やされよう…。
ドヴォルザーク: チェロ協奏曲ロ短調 Op.104:第1楽章
ドヴォルザークの、かつての叶わなかった想いも詰まった「鎮魂の曲」でもある、ドヴォルザーク:チェロ協奏曲の解説です。
【楽曲を解説】ドヴォルザーク:チェロ協奏曲

あのブラームスを感動させたドヴォルザーク:チェロ協奏曲の、こんな解説があります。
(ドヴォルザークは)ニューヨークのナショナル音楽院の院長として、ほぼ3年間アメリカに滞在(中略)
この期間の最後の大作としてチェロ協奏曲に取組んだのだった。
それだけに、そこには、アメリカの民謡や黒人の音楽から消化した語法がないわけではない(中略)
ブラームスは、死去する5か月ほど前にこの曲を知り、「こういう協奏曲を書けるとわかったら、自分で作曲してみたのだが」と語った。
出典:門馬直美 著 「管弦楽・協奏曲名曲名盤100」P114より引用
なんとも憂いを帯びたメロディと情感のこもった名曲、ドヴォルザーク:チェロ協奏曲です。
これには、こんなエピソードも遺っています。
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲を完成させてすぐ、勤め先であるナショナル音楽院のあるニューヨークから、故郷であるチェコへ帰国します。
そこで、ドヴォルザークに「ヨゼフィーナが亡くなった」との悲報が届きます。
この「ヨゼフィーナ」は、20代の頃のドヴォルザークが、ピアノ教師をしていた頃の生徒でした。
このヨゼフィーナに思いを寄せていたドヴォルザークは、プロポーズをするところまでいきますが、あえなく失恋。
その後、縁あって、そのヨゼフィーナの妹であるアンナと結婚したという過去があったのです。
その後は、幸福な家庭を築いていたドヴォルザークですが、亡くなった人は、プロポーズまでした「初恋の人」であり、その後も親しい交流があったわけです。
やはりショックは大きかったようです。
ピアノを教えていた当時ドヴォルザークは、声楽も学んでいたヨゼフィーナに何曲かの歌曲をプレゼントしていました。
そのうちの「一人にさせて」という歌をヨゼフィーナは気に入り、よく歌っていました。
そのようなこともあり、すでに完成していた《チェロ協奏曲》の第3楽章に、64小節もの加筆を行います。
そう、ヨゼフィーナが好んで歌っていた「一人にさせて」のメロディを、そこに書き入れたのでした。
このドヴォルザーク:チェロ協奏曲が、どこか、さみしさや悲しみを感じさせるのは、そんなエピソードが、あったからなのだと言われています。
また、ドヴォルザークが勤めたアメリカのニューヨーク・ナショナル音楽院で出会った黒人たちから教わった「黒人霊歌」。
この癒やしの要素も、このドヴォルザーク:チェロ協奏曲の中にも息づいているとも、言われてもいますね。
【各楽章を解説】ドヴォルザーク:チェロ協奏曲

この曲は第1楽章から第3楽章までの3曲で成り立っています。
第1楽章 アレグロ(速く)
切々として、憂いを帯びたクラリネットによる歌から始まります。
その歌に木管楽器や弦楽器が、重なっていき、音楽はいきなり盛りあがります。
ボヘミアの民族舞踊の、なんとも牧歌的な雰囲気と、さみしさなどが、表現されます。
それとともにドヴォルザーク:チェロ協奏曲の主役である、チェロが歌い始めます。
そして、感動のドヴォルザーク:チェロ協奏曲の役者が、そろい劇的な展開をみせていきます。
第2楽章 アダージョ・マ・ノン・トロッポ(ゆっくりと、しかし、ゆっくりすぎないように)
非常にメランコリック(感傷的)でありながら、そのうちに美しさを秘めた楽章です。
解説で、歌曲「一人にさせて」を第3楽章に書き加えたことは書きましたが、この第2楽章にもメロディが入っています。
ここでも、いわば「ヨゼフィーナのテーマ」が現れるところが、聴くものの感傷を誘います。
全体的に優美で情緒あふれる楽章となっています。
第3楽章 アレグロ・モデラート(ほどよく速く)
非常に力強く演奏される楽章ですが、どこか憂いは残ります。
ただ、とても優しいボヘミアの風を強く感じる楽章ではあります。
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲のフィナーレを飾るにふさわしい「輝く希望」をも感じさせる素晴らしい楽章に仕上がっていると思います。
【5枚の名盤を解説】ドヴォルザーク:チェロ協奏曲

堤剛:チェロ スデニェック・コシュラー:指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団
アルパカのおすすめ度★★★★★
正直なところ、個性は強く出ていません。
ある意味、インパクトにも、とぼしいかもしれません。
そして、淡々としている。
…なのに、なのに、アルパカにとっての、ドヴォルザーク:チェロ協奏曲の…
超名盤なのです。
技巧、センス、神がかり的なインスピレーション。
そんな、スゴイ天才的チェリストの演奏が多く、素晴らしい感動を与えてくれる名盤が、目まぐるしいほど、存在しています。
…なのに、なのに、長い時間をかけて感動が朽ちない名盤というものが、あるものなのです。
それが、堤剛のチェロとともに、コシュラーと、チェコフィルが組んで録音された名盤です。
これは、協奏曲というよりも、交響曲のような印象です。
指揮者コシュラーの、ドヴォルザークをリスペクトして止まない高貴な精神性と、その思いをなんとか実現せんとする堤剛の素晴らしいシンクロの精神。
そして、指揮者コシュラーと堤剛の思いを、なんとかこの世に形として残したいという思いのチェコフィルの楽団員たちの熱い思いが伝わって来ます。
ドヴォルザークを聴く上での醍醐味は「目の前に広大に展開するボヘミアの自然のイメージと、その温かみ」だと思います。
そんなドヴォルザークの音楽性を愚直なくらいに、まっすぐに表現された名盤中の名盤です。
今では非常に安く手に入るようになったようですね。
うれしい限りです。

ジャクリーヌ・デュプレ:チェロ ダニエル・バレンボイム:指揮 シカゴ交響楽団
アルパカのおすすめ度★★★★★
堤剛とは、対極を行く、女流チェリスト、デュ・プレのチェロの男性的で力強い超絶技巧が、楽しめます。
この「完全主役のチェロ」の歌の素晴らしさを前に、バックの楽団は、チェロを華やかにひきたてる脇役と化します。
しかし、この名盤は、そんなコントラストを堪能して、骨太で、カッコいい痛快なチェロを存分に味わうためのもの。
あまりにも熱い、デュ・プレの「歌」「語り」「思い」が心の刺さる、そんな感想の名盤です。
ピエール・フルニエ:チェロ ジョージ・セル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
アルパカのおすすめ度★★★★☆
語りすぎない「香り高い気品のフルニエのチェロ」を、知的なサポートで、完成へ導いたセルの指揮に、舌を巻く名盤です。
フルニエのチェロの、自己主張の強くない、なめらかな音の美感は「それそのものが、最高の自己主張」と言えそうです。
そして、それゆえに見事としか言いようがない音世界という感想。
他に比べると、「ボヘミアの自然」の表現という趣きは、少ないかもしれません。
でもチェロと管弦楽の磨き抜かれたワザは、それこそ他に比べようがない美しさの名盤ですね。
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:チェロ カルロ・マリア・ジュリーニ:指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
アルパカのおすすめ度★★★★☆
ロストロポーヴィチのチェロの演奏は何種類かあります。
その中でも、名盤のほまれ高いのが、カラヤン、ベルリン・フィルの演奏ですね。
2人の大巨匠がタッグを組んだまさしく超絶名演です。
ただ、アルパカとしては、その骨太で、押しの強い力強さに、イマイチ入り込めない感があります。
そんなわけで、ロストロポーヴィチの演奏の中でも、ジュリーニ、ロンドンフィルとのコンビ版が、アルパカのオススメ名盤なのです。
柔らかく優美なジュリーニの演奏の中に、普段よりも少しだけ肩の力を抜いた、いい意味での線が細めの、表現をするロストロポーヴィチのチェロが心に沁みてきます。
もともとが力強い表現をするロストロポーヴィチが、チェロを優美に奏するからこそ、その深みやコクが、グッと増す名盤なのですね。
とくに切々と、謳い上げられる第2楽章の憂いを帯びた響きは絶品ですよ。
普段は、ロストロポーヴィチ、カラヤン版を聴きながらも、余裕があったらぜひ、ジュリーニ指揮の名盤にも触れてみてくださいね。
ヤーノシュ・シュタルケル:チェロ アンタル・ドラティ:指揮 ロンドン交響楽団
アルパカのおすすめ度★★★☆☆
チェロの繊細な音はドヴォルザーク:チェロ協奏曲には、合っています。
ドラティとロンドンフィルのサポートも、シュタルケルのチェロの特性を支えて、素晴らしい。
全体として、感性的な叙情性を表現した、「恋するドヴォルザーク」の、ヨゼフィーナを想う気持ちとは、こういう感覚だったのかな。
そんな感想を持てる、名盤ですね。
【解説と名盤、まとめ】ドヴォルザーク:チェロ協奏曲

さて、ドヴォルザーク:チェロ協奏曲の名盤の紹介と、解説はいかがでしたか?
人の本来、持ってるい優しさと、それゆえに感じる、さみしさとが交錯するドヴォルザーク:チェロ協奏曲…。
そんな中にボヘミアの自然のイメージや、黒人霊歌の波動も流れるドヴォルザークの名曲でもありますね。
じっくりとドヴォルザーク:チェロ協奏曲に耳をすませば、きっと日ごろの疲れや、いらだちを癒やしてくれることと思います。
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事↓
ドヴォルザークのもっとも有名なこんな曲もオススメです。
文中にあった「黒人霊歌」との関係を書いたこんな記事はいかがですか?
ボヘミアの大自然を感じるスメタナの名曲もアリですね!