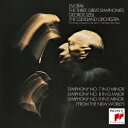なんと明るく痛快!
幸福感に満ちた
傑作交響曲♫
西欧的伝統と民族性!
ドヴォルザークの描いたチェコの田園は…、
- スカッ!と、爽快!
- キラッ!と、まぶしい!!
- ドドンッ!と、壮観!!!
さて、今回は、
聴いてるだけで「元気10倍で勇気100倍!!」
…な、ドヴォルザーク《交響曲第8番》解説とおすすめ名盤を紹介です。
【解説】ドヴォルザーク《交響曲第8番》

ドヴォルザーク《交響曲第8番》のについてのこんな解説があります。
西欧的たらんと(中略)誠実愚直な田舎者の真剣な目差しは、第7交響曲まででたくさん。「ドボさんには、無理しないで、カントリー・スタイルでいて欲しい」。 内心、ブラームスだってそう思っていたのでは……。(中略)第3楽章では、まだ名ワルツ編曲者ブラームスの体臭がいくらか残っているとしても、フィナーレはまったくの「ブラームスよ、さようなら……」なのである。(中略)ハイドンの喜びに満ちたロンドの伝統、異国趣味的舞曲調の理想的開花がある。民族衣裳に着がえたドボ先生のはしゃぎぶりは盛大に楽しい。
出典:諸井誠 著 「交響曲名曲名盤100」P144より引用
ドヴォルザーク《交響曲第8番》の持つパッションと民族性の魅力。
読み手にバイブレーションを込めて伝えてくる諸井誠先生の解説が素晴らしいですね。
さて、1889年、ドヴォルザークが48歳の夏にボへミアのヴィソカー村にある別荘に滞在し《交響曲第8番》を作曲します。
ボヘミアのヴィソカー村はドヴォルザークがとても気に入っていた土地でドヴォルザークの友人への手紙でも、
「ここではとても幸福を感じる」
としたためています。
まさしく、そんな大好きな土地で作曲されたからこそ「幸福」を象徴するような、
- 明るくて
- 華やかで
- 優しさに満ちた
そんな素晴らしい名曲が生まれたのかもしれませんね。
ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番《新世界より》ですが、アルパカがドヴォルザークの交響曲にハマった最初が実は《交響曲第8番》でした。
なぜなら、「幸福感と楽しさに満ちあふれいて聴いていて心から喜べる」そんな交響曲であるからです。
第9番《新世界より》がチェコのボヘミアの大地への郷愁から作曲されたのだとしたら、《交響曲第8番》はボヘミアの大地そのものと言えるかも…。
そう、言い換えれば「幸福感そのもの」と言える名曲でも、またあるのですね。
完成は1889年11月8日、プラハ。
初演は1890年2月2日、ドヴォルザーク自身が指揮を執って行われました。
【各楽章を解説】ドヴォルザーク《交響曲第8番》

それでは、各楽章について解説します。
ドヴォルザーク《交響曲第8番》は第1楽章から第4楽章までの4曲で成り立っています。
第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ(陽気に速く)
「これは田園の夜明け?」
チェロが響けばホルンが歌い、そしてやってくるクラリネットのささやき…。
そして躍動、楽器群!!
- ボヘミアの自然に降り注ぐ太陽
- バリバリと大地を破って芽吹いてゆく木々
- 鳥たちは歌い、風は草原を渡りゆく
そう、まさしくそれは、
ボヘミアの自然に満ちる幸福の讃歌!!
ドヴォルザーク《交響曲第8番》の始まりを飾る、勇壮でありながらも優美な楽章です。
第2楽章 アダージョ(ゆっくりと)
静かさを含んだ調和的な幸福感、そよぐ風のたおやかさ。
太陽の光も穏やかに降りてきます。
途中、暗い影も落ちますが、空を曇らせ、大地にこぼれる雨の風景でしょうか?
しかし、この雨もすぐに止み、再び調和的な幸福感は戻ってきます。
そして、続く、どこまでも続く、そして、いつまでも続く自然の恵みによる「うるわしき時の流れ」。
そんな美しい楽章です。
第3楽章 アレグレット・グラジオーソ:モルト・ヴィヴァーチェ(やや速く優雅に:とても速く)
解説にありますが「ブラームスの体臭がいくらか残っている」とてもメランコリックで美しい旋律に満ちた楽章です。
もちろんその中にはドヴォルザークらしい民謡的魅力や、リズム感もあります。
「とりあえず第3楽章だけでも聴いてみる」というのもアリ。
旋律作家、ドヴォルザークの素晴らしさが再確認できる楽章でもあります。
第4楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ(速く、しかしあまり速すぎないように)
はじまりは、ファンファーレ!
トランペットによる勇壮なソロが歌います!!
すると、静かに鳴り出すチェロをメインにした静かなささやきと合奏…。
しばらくささやくと、だんだんと盛り上がっていく楽曲!
その後は彩り豊かに、そして自在に変化して展開するドヴォルザーク《交響曲第8番》のフィナーレ。
- 元気に、
- 華麗に、
- 幸福感いっぱいに、
盛り上がり、
盛り上がり、
盛り上がり、感動的に幕を閉じていくのです!
【名盤3選の感想と解説】ドヴォルザーク《交響曲第8番》

ジョージ・セル:指揮 クリーヴランド管弦楽団
無料体験amazonミュージックUnlimitedで聴けます♫
アルパカのおすすめ度★★★★★
【名盤の解説】
1970年録音のEMI版の評価が非常に高いのですが、今回紹介させていただくのは1958年録音のCBS版の名盤です。
- 明るさ!
- 初々しさ!!
- 幸福感!!!
が強く感じられるからです。
EMI版ももちろん素晴らしいです。
均整が取れていて、ほどよい重厚感もありますし、なんと言っても晩年のジョージ・セルの持つ心地よい円熟味があります。
これは好みの違いと言えますが、アルパカとしては1958年版の名盤が好きなのです。
録音は古いので「音質重視向き」の方には満足を与えてくれないかもしれませんが、過去、この名盤からたくさんの元気をもらえました。

ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮 シュターツカペレ・ドレスデン管弦楽団
無料体験amazonミュージックUnlimitedで聴けます♫
アルパカのおすすめ度★★★★☆
【名盤の解説】
セル指揮の名盤を超えるような「元気な名盤」が聴きたい時はこちらです。
テンポは速め、勇ましく展開するドヴォルザーク《交響曲第8番》は心の底から元気を引き出してくれます。
またそれとは対象的に「調和的な響きが魅力の第2楽章」も、「メランコリックな美しさのある第3楽章」も素晴らしい。
そう、シュターツカペレ・ドレスデン管弦楽団 の芳醇な響きが深い味を出しています。
少し元気すぎる感もありますが、地味でつまらない毎日にガツンと効く(聴く)ビタミン剤になること間違いなしです。
カルロ・マリア・ジュリーニ:指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
無料体験amazonミュージックUnlimitedで聴けます♫
アルパカのおすすめ度★★★☆☆
【名盤の解説】
- 香り高くて
- 気高くて、
しかも、
- 思いやりにあふれている
そんな名盤です。
本来、おだやかで誠実な性格なドヴォルザークです。
ただただ「明るく元気な演奏」よりも意外とこんな演奏をドヴォルザーク自身は喜ぶのかも…なんて思ってしまいます。
カルロ・マリア・ジュリーニの指揮する音楽は、いついかなる時にも人間としての体温の暖かさを忘れることのない紳士の姿を思わせます。
そういった意味で「癒やしや安心感が欲しいとき」に聴きたい名盤と言っていいと思います。
【まとめ】ドヴォルザーク《交響曲第8番》

さて、ドヴォルザーク《交響曲第8番》の解説とおすすめ名盤はいかがでしたか?
- 明るくて
- 華やかで
- 優しさに満ちた
名曲交響曲です。
このなんとも幸福感の感じられるドヴォルザーク《交響曲第8番》を聴ききながらチェコ、ボヘミアの大自然をイメージして、自分、取り戻しましょ…。
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は、以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
関連記事↓
ドヴォルザークの名曲交響曲だったらこの2曲
明るく元気なシューベルトのこんな交響曲もいかがですか?