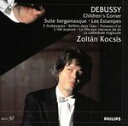キラリ、キラリと光る「水の反映」
毎日、疲れて前へ踏み出せない
そんな時に聴きたい1曲♫
今日も上司に叱られて、
いっぱい、いっぱい落ちこんで、
気がつきゃ、うつむき歩いてる…。
「そうだ…『水の反映』でも聴こうかな…♫」
- 【楽曲を解説】ドビュッシー:水の反映《映像第1集より》
- 【各曲を解説】ドビュッシー:《映像:第1集と第2集》
- 【4枚の名盤を解説】ドビュッシー:水の反映
- 【解説と名盤、まとめ】ドビュッシー:水の反映《映像第1集より》
【楽曲を解説】ドビュッシー:水の反映《映像第1集より》

映像的で、印象的。
そんな、ドビュッシー:水の反映に関する、こんな解説があります。
映像=イマージュという題名ほど、ドビュッシーの音楽性を見事に表
わしている言葉はない。ドビュッシーは、まさにイマージュの世界に生き、イマージュの中に遊び、イマージュと共に消えていく作曲家なのである。
ラヴェルの《水の戯れ》に刺激されて、生まれた曲であることは、よく知られている。
出典:諸井誠 著 「ピアノ名曲名盤100」P170より引用
たしかに、ドビュッシー の《水の反映》は、「水のイマージュ(想像)」の世界という感想です。
揺らめく水面にキラリ、キラリと光を反射するさまが、ドビュッシーの独特な、音楽的タッチで描かれています。
とてもドビュッシーらしい、印象的で、美しい1曲だと思います。
また、解説にも、ありましたが、同時代を行きた、ラヴェルの《水の戯れ》というピアノ曲も「水」がテーマです。
ドビュッシー:水の反映と比べても、耳を通して心に届く、イマージュ(想像)は違います。
それは、ドビュッシーの《水の反映》は映像的で、絵画的、それこそ「印象派といわれる絵画」という感想ですね。
それに対して、ラヴェルの《水の戯れ》は、知的で明解な表現に感じます。
よく、人間の精神活動には、「知・情・意(ち・じょう・い)」の3つに分けられると言われます。
これをもとに考えますと、
ドビュッシーは、「情」つまり、「感情」や「感性」の特徴が強く、
ラヴェルは、「知」つまり、「知性」や「理性」の特徴を感じます。
でも、さまざまな「感じ方」や「比べ方」は、あるかもしれませんね。
結局、最終的に、「音楽は、理屈抜きに、思い切り楽しむというあり方がいい」のかもしれません。
モーリス・ラヴェル《水のたわむれ》については、こちらの記事がオススメです。
【各曲を解説】ドビュッシー:《映像:第1集と第2集》

それでは、本記事のテーマである「水の反映」が収録されているドビュッシー作曲の《映像》の第1集と、第2集。
これらについての、解説をしていきたいと思います。
《映像》第1集
1.「水の反映」
こちらは冒頭で解説しました。
2.ラモーを讃えて
16世紀に、フランスで活躍した作曲家であり、音楽理論家の、「ジャン=フィリップ・ラモーを讃える気持ち」から、作曲されました。
たんたんとして、展開する音楽は、歴史ある、グレゴリオ聖歌の音階を思わせるという感想です。
しかし、その中にドビュッシーらしい、絵画的に描写された音楽性が感じられます。
そして、それが、「ラモーを讃えて」という曲の特徴となっているのです。
3.「動き」
とても速いピアノのリズムが、ドビュッシーの印象的な色彩で、広がりを見せていきます。
ここで、ドビュッシーの印象派的音楽は、わずかな明快さを帯びながら、はじける感じになります。
《映像》第2集
1.「葉ずえを渡る鐘」
第2集からは、少し倦怠感を含んだ特徴を、帯びてきます。
「葉ずえを渡る鐘」という曲も、どこか、手触りの冷たい感じでありながら、スピード感もありますね。
2.「荒れた寺にかかる月」
なんとも和風テイストな題名の曲なことでしょう。
ちょっとデカダンス(退廃的)な印象があるのは、「ドビュッシーの生きた当時の時代の流れ」の表れかもしれません。
それから、ドビュッシーの活躍した時代は「ジャポニスム」(浮世絵などの日本の芸術を趣味とする流れ)が流行った時代。
ドビュッシーも浮世絵に影響を受けた曲を書いています。
これらの雰囲気がこの曲にも、漂っているという感想です。
3.「金色の魚」
金色の魚が、池の水を弾かせながら、思い切り、「泳ぐ」、「踊る」、「遊ぶ」。
そんな、ちょっと可愛らしいような、イマージュという特徴の1曲ですね。
【4枚の名盤を解説】ドビュッシー:水の反映

ゾルタン・コチシュ:ピアノ
アルパカのおすすめ度★★★★★
コチシュのキラメキが素晴らしい。
とくに、ドビュッシー:水の反映の、水のゆらめき、反映がここまで、キレイに感じられるのは驚きです。
「音楽の印象派」としてのドビュッシーを楽しみたい方には、すこし、キラメキの表現が行き過ぎな面もありますが、楽しめる1枚だと思います。
ベネディクト・ミケランジェリ:ピアノ
アルパカのおすすめ度★★★★☆
音の粒が、光そのものの輝きを放ってますね。
その卓越した技巧と、感性が、素晴らしい。
堂々としていながら、その「柔らかい感性との同居」が出来るのは、ミケランジェリの不思議な魅力。
じっくりと、音の優美さを味わいたい名盤です。
サンソン・フランソワ:ピアノ
アルパカのおすすめ度★★★★☆
少しゆったり目の、粋な表現がニクイ名盤。
カッコよさの中に、純粋なピアニズム、技巧が潜んでる。
フランスの作曲家の音楽なら、この人の名盤は、一度、聴いておきたい。
それが、うまさとオシャレが息づいてるサンソン・フランソワの名盤です。
ワルター・ギーゼキング:ピアノ
アルパカのおすすめ度★★★☆☆
録音は古く、音はよくありません。
でも、どこかいい意味で、冷たいイマージュの、ドビュッシー《映像》。
こんな風に、感情を少なめに、クールなイメージで表現されると、ピリッと目が覚める感覚を覚えます。
あまり感性におぼれずに、楽しみたい方には、この1枚がいいのではないでしょうか。
【解説と名盤、まとめ】ドビュッシー:水の反映《映像第1集より》

さて、ドビュッシー:水の反映」の名盤の紹介と、解説はいかがでしたか?
毎日が忙しくて、セカセカと流れていき、いつもソワソワ、イライラ。
せめて、1日の終りの寝る前に、静かな時間をとって、「自分を取り戻したい」ものです。
「う〜ん、なかなか、いい精神状態に戻せないな…」。
そんなときは、ドビュッシー:水の反映を、静かに流して、心を取り戻すのを、手伝ってもらうというのも、アリですよ。
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事↓
「月の光」に癒やされる、こんなピアノの名曲も…。
ギリシャ神話に登場するパーンの神さまを描いて、親しみやすい調和の名曲