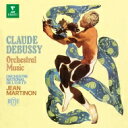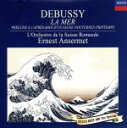午後のひととき
ひっそりと
楽しい夢みて、遊ぼうよ…。
あたたかく、よく晴れた午後のお昼寝。
最高に気持イイですね!
ギリシャ神話に登場する「パーン」という神さまも、お昼寝が大好き。
そして、その姿は、
- 額には、ヤギのような2本の角
- アゴには口ひげ
- 2本の足はヤギのような足
そんな「パーン」という、神さまのイメージから、作曲されたのが「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」です。
今回は、ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲の感想と解説です。
さあ、お昼寝好きのあなた、さっそく名盤を聴いてまどろみましょう♫
- 【歴史を変えた】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲を感想と解説
- 【マラルメの詩から発想】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲の感想
- 【3枚の名盤の感想と解説】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲
- 【解説と名盤、まとめ】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲の感想
【歴史を変えた】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲を感想と解説

ゆったりとした瞑想的な、名曲、「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」は、1892年から1894年にかけて作曲されました。
そして、じつは、音楽の歴史を塗り替える斬新な試みが行われた1曲だったとの感想を持っています。
こんな解説があります。
ドビュッシーは(中略)ロマン主義的な音楽に満足できなくなり、印象主義の音楽を開発するようになる。(中略)
喜怒哀楽(の表現というよりは、)神秘的な気分を表出の対象とした。
印象主義の美術も、これと多くの類似点を持っていて、(中略)色彩感のある光と空気を描くことに重点をおき(中略)描こうとする。
この解説にあるように、それまでの音楽は「喜怒哀楽の感情表現」や「型」を重視した音楽作りがメインでした。
これを、ロマン派の音楽といいます。
しかし、ドビュッシーはロマン派の音楽から自由になって 、「光」や「空気」のようなものを「淡い色彩で描く」際に感じる感想を音楽において、表現してみせました。
それが、音楽の印象派のはじまりでした。
そして、その始まりの曲が、この「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」なのです。
これは「歴史的」と言っていいのではないかとう感想を持ちます。
もともとは、ロマン派の巨人とも言えるワーグナーに傾倒していたドビュッシー。
現代の「アイドルの追っかけ」よろしく、ワーグナーを追いかけて、ウィーンやイタリアまで、足を運んだこともあるドビュッシーでした。
しかし、その後、ドビュッシーはドビュッシーなりに、「自分の追い求めるべき音楽世界」を見つけていったと言っていいかもしれませんね。
【マラルメの詩から発想】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲の感想

「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」は、マラルメの詩、「半獣神の午後」をもとに作曲されました。
ここで、感想と解説をしておきます。
よく晴れた午後、牧神パーンは葦(あし)で作られた笛を口にくわえて、うつろな音を楽しんでいました。
その意識は、夢と現実を行ったり来たりしていました。
牧神パーンは、午後の昼寝が大好きでした。
そんなボンヤリとした時を過ごしていると、目の前の水ぎわに、美しいニンフ(女神)たちが水浴びにやってきました。
その美しさは輝くばかりのまぶしさです。
牧神パーンは、思い立ち、ニンフを追いかけようと、立ち上がります。
すると、ニンフたちは、それに気づいて足ばやに逃げ出します。
結局、逃げおおせたニンフたち。
思いが果たせずに立ちすくむ牧神パーン。
そして、再び、うつろな時がやってきます。
葦(あし)の笛をむなしく吹きながら、
うつろな午後の時は、おもむろに過ぎてゆきます。
ちなみに、この牧神パーンが吹く葦(あし)の笛ですが、もともとは、ニンフでした。
しかし、牧神に追いかけられて、つかまった際に、パーンを嫌い、葦(あし)の笛に姿を変えてしまったとのお話しもあります。
牧神パーンは、いつも片思いなのですね。
以上、原文とは違いますが「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」を聴いた上での感想を、意訳させていただきました。
あしからず、ご容赦ください。
いずれにしても、イメージにとらわれすぎずに、自由な気持ちで、「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」を聴くことがオススメです。
そんな個人個人の、自由な感想を大切にして、聴くことが印象派芸術の願いであり、歴史でもあるのですから…。
さあ、日ごろの喧騒から、心を解き放ち、透明な時間をすごしましょう。
【3枚の名盤の感想と解説】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲
ヘルベルト・フォン・カラヤン:指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
アルパカが人生で初めて聴いた磨き抜かれた美の極みの名盤。
「こんなにもおだやかで、透明感のある音楽、聴いたことがない…」。
「演奏自体も、この世のものとは思えない、光そのものという感覚」。
「とくにフルートの光が優しく、輝かしい」。
そんな感想とともに、「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」が大好きな曲となるキッカケになった名盤です。
いつでもスマホをポチって聴けるようにしているカラヤン指揮の「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」はいつも一緒のアルパカの名盤。
「いい景色に出会ったらすぐポチる」
すると、その「いい景色」とシンクロした「洗練された透明な美」が心の世界をおおいつくします。
オススメ度★★★★☆

(※1985年録音盤です。文中にあるアルパカが初めて聴いたのは1964年録音盤でした。)
ジャン・マルティノン:指揮 管弦楽団
アンニュイな午後に聴きたいのならこの1枚。
牧神パーンの、葦(あし)の笛の音色は、ちょうど、このアルバムのフルートの音の雰囲気に近いという感想です…。
この、まどろむように美にふける、牧神パーンのフルートと、明るく、まぶしいニンフたちが、かけ足で逃げてゆく感じも美しい。
「こんなにまどろんでいては、そりゃあ、ニンフたちに逃げられますよ。牧神パーンさん。」
そんなツッコミを入れたいくらいに静かに愉しめるアルバムです。
オススメ度★★★☆☆
エルネスト・アンセルメ:指揮 スイスロマンド管弦楽団
幻想的でありながら、一音一音はくっきりと鮮明で曖昧(あいまい)さは感じません。
アンセルメの持つ「気品を含んだ牧歌的」音世界という感想です。
この特徴は「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」にはピッタリと言う感想ですね。
ただ、「うつろで、アンニュイな雰囲気」を存分に楽しみたい方には、おすすめできません。
ただ、どこかフランス的な華やかさの香りを含んだ歴史に残る名盤という感想を持っています。
オススメ度★★★☆☆
【解説と名盤、まとめ】ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲の感想

さて、「ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲」の名盤の紹介と、感想はいかがでしたか?
このような神話を題材とした音楽物語には、癒やされる名盤が多いものです。
作曲者自身も空想が働いて、インスピレーションが降りやすいのかもしれませんね。
このような音楽たちはきっと長く歴史に残ることでしょうね。
さあ、あなたも牧神パーンになって、午後のお昼寝といきませんか?
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ドビュッシーのこんな癒やしの1曲もいかがですか?↓
秋の雰囲気で癒やされたいなら…↓