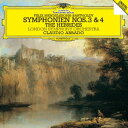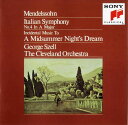広がる海原
くだける白波
さあ、神秘の洞窟に踏み込もう
情景描写の名曲!
メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》を聴いて実際のフィンガルの洞窟を耳を使って見(聴き)に行こう!!
メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》の解説とおすすめ名盤を紹介です。
- 【成りたちを解説】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》
- 【楽曲を解説】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》
- 【3枚の名盤の感想と解説】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》
- 【解説と名盤、まとめ】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》
【成りたちを解説】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》

メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》の音の美しさを思わせる、こんな解説があります。
(フィンガルの)洞窟の風景を描写的な手法をとり入れながら描いたもので、岩にくだける白波、飛びかうかもめの姿、神秘的な洞窟などを暗示する。
海に取材した音楽を古今の他の作曲家も数多く書いているが、このメン
デルスゾーンのものほど美的であり、しかも端麗な作品は多くはない。のちのワーグナーは、この曲をきいてメンデルスゾーンを第一級の風景
画家と評したときもあったほどである。出典:門馬直美 著 「管弦楽・協奏曲名曲名盤100」P48より引用
【作曲のエピソード】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》
メンデルスゾーン20歳の頃、有名な「スコットランド交響曲」を作曲する動機となったホリルード宮殿を訪れます。
その流れで、1829年8月7日にメンデルスゾーンは「フィンガルの洞窟」にも訪れたわけです。
曲はこの「フィンガルの洞窟」に響く音から得たインスピレーションにまかせてペンを走らせたものです。
冒頭の主題を素早く書きあげたメンデルスゾーンは、すぐさま実家の姉へ向けて手紙を送ります。
「僕が、ヘブリディーズ諸島で受けた大きな感動を分かち合いたいんだ。降りてきたインスピレーションを、まっさきに姉さんに届けたかったんだ。」
また、解説には「ワーグナーは、この曲をきいてメンデルスゾーンを第一級の風景画家と評した」とありました。
そして、実際、メンデルスゾーンは絵を描くことも得意としていました。
感じたことを「音」としてはもちろん「手紙」としても「絵」としても表現できるなんてメンデルスゾーンは、なんと多彩な才能を持ち合わせていたことでしょう。
【呼び名の由来】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》
メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》は「序曲」と名づいていますが、曲そのものは独立した作品です。
風景描写的な内容を持っている、言わば標題音楽的な曲です。
そして、このかたちが後の「交響詩」というジャンルのもとにもなったと言われています。
交響詩とは「詩や物語、 絵画や情景」などを音として表現したものですね。
ちなみにこのメンデルスゾーン:《フィンガルの洞窟》は、《ヘブリディーズ》と呼ばれることもありまし、海外ではむしろ《ヘブリディーズ》と呼ぶことが多いです。
これは、このフィンガルの洞窟がスコットランドにある「ヘブリディーズ諸島」に存在する洞窟のためです。
また、メンデルスゾーン自身も楽譜の一部に《ヘブリディーズ》と記載した跡が残されているためでもあります。
ただ、日本国内では《フィンガルの洞窟》と呼ぶことが一般的ですね。
また「フィンガル」とは、かつてヘブリディーズ地方を統治していた伝説的な英雄の名前からとられたものでもあるとも言われています。
【楽曲を解説】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》

では、曲の解説に入りましょう。
フィンガルの洞窟の、岩を叩く白い波しぶきが打ち寄せる音の様を、ヴィオラ、チェロ、そして、ファゴットは奏でます。
これが第1主題となるわけですが、これにさまざまな楽器が加わりながら音楽は展開するわけです。
そして、その波の音は、時には静まり、時には荒れながらドラマティックに展開していきます。
劇的な動きを見せながら、最後は再び第1主題に戻り、静かに波の音が落ちつきながら曲はフィナーレを迎えるわけです。
実際、メンデルスゾーンがフィンガルの洞窟を訪れた時、嵐の日であったと言われています。
そんなこともあり、美しい風景とともに荒れた海の様相と音も描かれたものと思われます。
【3枚の名盤の感想と解説】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》

クラウディオ・アバド:指揮 ロンドン交響楽団
アルパカのおすすめ度★★★★★
【名盤の解説】
ゆったりと、しかし力強く波が岩を打ち付ける音のさまが、堂々とした演奏で再現された名盤です。
しらじらと夜が明けていくとともに波の動きにも変化が生じて、海面が七色に変化していくという感想です。
そんな見事な色のグラデーションが音で表現されている名盤でもあります。
オットー・クレンペラー:指揮 フィルハーモニア管弦楽団
アルパカのおすすめ度★★★★☆
【名盤の解説】
フィンガルの洞窟の奥深さと、その深遠をのぞくような重厚な名盤です。
波はいたって穏やかですが、時に盛り上がるその波は大きな音ともに岩に突撃し白く砕け散っていく。
そんな感想です。
しかし、その波の音は急ぐことも、あせることもないという感想でもあります。
本来、軽やかで明朗なメンデルスゾーンの音を、ずっしり重厚な表現をした深い色合いの性質の音を持つ名盤です。
ジョージ・セル:指揮 クリーヴランド管弦楽団
アルパカのおすすめ度★★★★☆
【名盤の解説】
すっきり知性的なつくりをしています。
どこか淡々としているところは「これは凪(な)いだ波か…」という感想をもつため、「動き」には若干とぼしいかもしれません。
しかし、こんな凪いだ波のたゆたう波の静かな音にこそ逆に神秘の深さという感想を持てる名盤でも、また、あります。
本来のメンデルスゾーンの「音の美感」を重視したという感想も持てる素晴らしい名盤ですね。
【解説と名盤、まとめ】メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》

さて、メンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》の名盤のオススメと、解説はいかがでしたか?
忙しい毎日のなか、なかなか旅行もままならないですね。
そうなると「どこか近場で開放的なところはないかしら?」と思うものです。
でも、
「ありますよ。」
というのがアルパカの答えです。
そう、クラシック音楽には美しい情景を描いた曲もいっぱいです。
さあ、再生スイッチをポチって「フィンガルの洞窟」を眺めながら日頃のストレス解消といきましょう!
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は、以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
関連記事↓
メンデルスゾーンのこんな開放的な交響曲も気持ちいい!!
www.alpacablog
こんな明るい冒険物語(交響詩)もいいっすね!