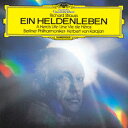「何かにいどむ!それが英雄の生涯!」
ビジネスパーソンだって、英雄の生涯!!
みんな、生きてるだけで、英雄だ!!!
(youtubeをポチって音楽を聴きながら読んでみてくださいね。”iPhoneの場合は全面表示されてしまったら2本指で内側にむけてピンチインしてください。”)
勇壮な交響詩
ひとにぎりの勇気が必要な時に聴きたい!
英雄の生涯の物語!!
- 【楽曲を解説】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》
- 【各楽章を解説】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》
- 【誰だって英雄を体験している!】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》
- 【3枚の名盤を聴き比べと解説】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》
- 【解説と名盤、まとめ】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》
【楽曲を解説】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》

R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》の「英雄的」なエピソードを含む、こんな解説があります。
この「英雄の生涯」を最後に、彼は、二度と交響詩の分野に、手をつけなかったのである。
(中略)
彼の音楽は、当時としては、冒険的な手法を用いたり、大規模なオーケストラを使ったりしたものだったため、保守的な批評家たちからは、激しい攻撃を受けたのである。
そこで彼は、この曲で、自分自身を英雄にしたてて、ひとりの英雄が、あらゆる苦難と闘い、それを、乗り越えていくさまを描くことで、批評家たちに一矢を報いたのであった。
いかにも闘志の人、R・シュトラウスの面目が躍如(やくじょ)としていて、おもしろい。
出典:志鳥栄八郎 著 「不滅の名曲はこのCDで」P132より引用
「ドン・ファン」や「死と変容」「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」など、R.シュトラウスには、壮大なモチーフ(動機)をもとにした、交響詩が多いです。
その交響詩の最後の曲が、R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》ということですが、最後にふさわしい、充実した音楽になっています。
また、音楽が表現しているところの物語も素晴らしいですね。
また、「この英雄とは、誰のことですか?」
こんな質問を投げかけられた、R・シュトラウスは、少し遠回しな言い方で、
「自分である」
と、答えています。
少し、ずうずうしく感じるかもしれませんが、
「生きてる限り、誰だって英雄」なんじゃないかなってアルパカは思います。
だって、日々を生きるって、それだけで大変だと、感じませんか?
ま、アルパカが、ただ、弱っちいだけかもしれませんが…(泣)。
会社員や、主婦や主夫、また、学生だって、毎日が戦いですよね。
そんな「英雄」の「戦いの生涯」が音楽として、昇華しているのが、R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》なのです。
【各楽章を解説】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》

R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》は、第1部から第6部までの6曲で成り立っています。
第1部 英雄
土けむりとともに、大地を駆け抜ける、英雄の勇ましい姿が想像できます。
R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》が描く、人生の壮大さをも連想させるR.シュトラウスらしい、華やかな1曲。
第2部 英雄の敵
管楽器のあわただしい響きから始まりますが、これは、解説にもあった、R.シュトラウスに向けられた、批評家たちの批判のイメージに聴こえなくもありません。
しかし、そんな批難にめげずに、しっかりと地に足をつけて、勇ましく立ち上がる姿が描かれているように感じます。
第3部 英雄の伴侶
英雄にも、やすらぎの時は、必要ですね。
たおやかな身のこなしの、英雄の伴侶の姿が、浮かぶようです。
伴侶自身のテーマは、ヴァイオリンのソロで奏でられ、優美な、おもむきに彩(いろど)られています。
第4部 英雄の戦場
壮絶な戦いの場面を想像させる、勇ましい1曲。
第3部の終わりに、 第2部の「英雄の敵」に出現した、管楽器のあわただしい響きが、現れます。
そして、その続きで、第4部の戦場のモチーフが現れます。
勇ましい管楽器であるトランペットが鳴り響くことによって、ただ、あわただしいだけではない、実力行使に出てくる敵!
これに、立ち向かう「英雄」の姿が、描かれます。
途中、伴侶の象徴であるヴァイオリンのモチーフもあらわれますが、これは英雄を精神的に支える伴侶の存在という意味なのでしょう。
金管楽器をはじめとした、楽器たちのすべてが、獅子のごとく咆えまくります。
そして、ラストで、冒頭の第1部、「英雄のテーマ」が復活!
戦いの勝利のイメージでしょうか?
その勢いのまま、次の曲へと、つながります。

第5部 英雄の業績
「英雄の業績」と、取れますが、凄まじい戦闘からの、華々しい凱旋!
そんなふうにも、聴こえますね。
音楽としても、R.シュトラウスの作曲した交響詩のメロディがあらわれます。
つまり、「ドン・ファン」「ツァラトゥストラはかく語りき」「死と変容」「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」「ドン・キホーテ」などのメロディですね
そんなことを知ると、このR.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》はまさしく。R.シュトラウスの交響詩としての集大成であったことがわかりますね。
第6部 英雄の引退と完成
老いを迎え、英雄としての人生をふり返る主人公。
田園にしりぞきながら、みずからの人生をふり返る英雄。
挫折を経験しながらも、たくましく人生を歩み、理解しあえる伴侶とも出会えた充実感を深く感じ取る英雄。
そして、伴侶に看取られながら、静かに、死を迎えます。
そして、壮大なる英雄の一大交響詩のフィナーレを、感動的に閉じていきます。
【誰だって英雄を体験している!】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》

「みんな、誰だって、英雄を体験している」。
生まれたばかりの赤ちゃんは、守ってくれる、おかあさんや、おとうさんを求めて冒険の毎日。
はじめての幼稚園や、保育園での、はじめてのお友だちとの出会いや、はじめてのお使いだって、この頃かもしれません。
また、学校での勉強や、テストや受験、恋愛や、就職だって、「未知に挑戦」しているという意味では、「英雄を体験」しているとも言えそうです。
なにも、混乱した国を立て直そうとか、巨大な敵から、国家を護ろうという大きな話しではなくとも、「生きてる限り、人はみんな英雄」なんじゃないかな?
そんな、「自分こそ小さな英雄」と思えば、R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》も、すごく身近な音楽として聴こえてくるかもしれませんよ〜♫
【3枚の名盤を聴き比べと解説】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》

ヘルベルト・フォン・カラヤン:指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
アルパカのおすすめ度★★★★☆
端正な顔立ちでありながら、「ここぞ!」というときには雄々しく吠える、英雄的な名盤。
英雄の人生の、さまざまなドラマを彩り、豊かに描ききった名盤。
あまりに完璧を求めすぎて、肌感的に少し冷たさはあるかもです。
ただ、超絶アンサンブルから繰り出される、音芸術の極地は、一度は聴いておいて損はない名盤!
ハンサムでカッコいい、注目の名盤です!
小澤征爾:指揮 ボストン交響楽団
アルパカのおすすめ度★★★★☆
堂々と厚みのある演奏で、飽きさせない名盤。
勇ましい英雄の一生が、骨太で充実した人生であったことが、うかがえる名盤でもありますね。
時に情熱的であり、また、時には情緒的である色彩豊かな、名盤とも言えそうですね。
ヘルベルト・ブロムシュテット:指揮 シュターツカペレ・ドレスデン

アルパカのおすすめ度★★★★★
その気高(けだか)さから来る、人徳と品格を感じる英雄は、聴いていて心地いい。
冒頭の第1部、「英雄」からして、かぐわしい名盤。
R.シュトラウスの音楽をこんなにも、ゆったりとした趣き(実際のスピードではなく)で、あたたかい表現をした名盤は珍しいですね。
アルパカが、個人的にオススメしちゃう、アルパカ的な名盤中の名盤!
この音世界は「名盤」の名にもっともふさわしい!
【解説と名盤、まとめ】R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》

さて、R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》の名盤の紹介と、解説はいかがでしたか?
日々の中で、「勇気」が必要な時も、あるものです。
そんな時は、R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》を聴いて、勇気を奮い起こすなんていうのも、アリかも…。
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事↓
こんなイタズラ物語もいいね!
こんないいメロディの宝庫も…