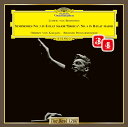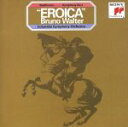ベートーヴェン自身
革命!
音楽新時代、来たる♫
う、裏切られた!
ナポレオンよ!
お前もか!!
自由への
- 大いなる希望
- 燃える情熱!
- 讃歌、高らかなり!!
ナポレオンへの尊敬と、その後の絶望が生んだ名曲♫
ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》、解説とおすすめ名盤を紹介です。
- 【解説】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》
- 【各楽章を解説】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》
- 【名盤3選の感想と解説】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》
- 【まとめ】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》
【解説】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》

楽曲解説
ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》についてのこんな解説があります。
ベートーヴェンははじめナポレオンに捧げるべく筆を進めていた。ところが、人類に平和と自由とをもたらす使徒として尊敬していたナポレオンが、こともあろうに皇帝に即位した、というニュースを聞いた時、彼は怒りのあまり即座に献呈をとりやめ、「シンフォニア・エロイカ」と題して出版したのであった。(中略)この曲が、耳の病気の悪化から、絶望のどん底に沈んだベートーヴェンが、不屈の闘志でそこからはいあがり、第2の人生を踏み出す出発点となった、記念碑的な作品である、ということも忘れてはならないだろう。
出典:志鳥栄八郎 著 「新版 不滅の名曲はこのCDで」P35より引用
フランス革命と言えばよく聞く言葉、
「自由・平等・友愛」
音楽家に限らず芸術家であれば憧れるものが「自由」。
フランス革命後の混乱を、破竹の勢いで収拾していくナポレオンに心酔するベートーヴェンはナポレオンに献呈するべく1曲の交響曲を作曲します。
これが交響曲第3番《英雄》であるわけですが、作曲当初は副題を「ボナパルト」と名付けていました。
ボナパルトとはナポレオンの苗字であることからベートーヴェンがどれだけナポレオンを尊敬していたかが伺えます。
しかし、解説にありますように「ナポレオンが、皇帝に即位した」と聞いた瞬間に副題を書き換えます。
そう「ボナパルト」から「シンフォニア・エロイカ(英雄的な交響曲)」へと…。
「奴もまた俗物に過ぎなかったか」
そんな言葉とともに…。
副題に込められた意味とは
改題の際、楽譜に書かれた「ボナパルト」の文字をペンでグシャグシャとかき消していおり、勢いで破れている部分もあるほどです。
ベートーヴェンの怒りの感情が伝わってくるようです。
この後「シンフォニア・エロイカ」と書き直した上で「ある英雄の思い出のために」と書き足してもいます。
この「ある英雄」とは誰のことなのかはハッキリしませんし「ナポレオン」という英雄と呼べる対象がいなくなってしまったため便宜的に付けただけかもしれません。
ただ交響曲第3番《英雄》という曲が「ウィーン古典派」の形式を打ち破って自由な発想で作曲されたことは確かです。
ベートーヴェンの交響曲第1番や第2番に見られる非常に整った古典派的な形式から開放されています。
- 「全曲50分を超える長さ
- 第2楽章を表題的に「葬送行進曲」と名付けた
- 第3楽章を「メヌエット」ではなく「スケルツォ」にした
- 終楽章が「変奏曲形式」である
これは、次世代に到来する「ロマン派」に通じる自由さが、すでに交響曲第3番《英雄》から芽吹いていると言えそうです。
ある意味「革命」であり、「英雄的」な勇気ある挑戦だったと言えます。
「ある英雄の思い出のために」
ベートーヴェンの耳の病が本格化してきたのも交響曲第3番《英雄》の作曲の少し前からでした。
有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」が書かれたのもこの頃で、「自死」を考えながらも勇気を出して思い直しをしたのも同じ頃。
この「ある英雄」とは、ある面ではベートーヴェン自身だったのでは…という気がしてきます。
もちろん、ベートーヴェン本人は自覚はなかったでしょうけれども、後世からみれば「ある英雄、ベートーヴェンの傑作」と言えるかもしれません。
ベートーヴェン自身が認めた最高傑作!
「自作でどれが1番出来がいいと思いますか?」
1817年、ベートーヴェンの亡くなる10年前、詩人クリストフ・クフナー(ベートーヴェン作曲、合唱幻想曲を作詞)は質問しました。
「エロイカ…」
間髪を入れずベートーヴェンは答えています。
この頃、ベートーヴェンは人生最後の交響曲第9番《合唱》
を作曲中でしたので、交響曲第9番の作曲後は答えが変わった可能性があります。
しかし、少なくとも交響曲第9番を作曲中の時点では、交響曲第3番《英雄》がベートーヴェンにとっての最高傑作だったことは間違いなさそうです。
初演:1804年12月ロブコヴィツ邸にて(非公開初演)
1805年4月7日アン・デア・ウィーン劇場にて(公開初演)
編成:
弦5部、フルート×2、オーボエ×2、クラリネット×2、ファゴット×2、ホルン×3、トランペット×2、ティンパニ×2
【各楽章を解説】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》

それでは、各楽章について解説します。
第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ
ジャン!
ジャン!
ドーミ、ドーソ、ドミソド〜♫
ゆったり優雅な序奏抜きのジャン!が2回続くと始まる主題が特徴的。
英雄が…時代精神がゆく!!
英雄とは、今までの閉塞した状況を打ち破って新たな時代を切り拓く精神そのもの!
そんな壮大で勇気を奮い起こしてくれる名曲、それがベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》第1楽章、最大の特徴です。
止まるな!
その歩みを止め、
出来上がった時点で、
時代精神たりえない!!
ただただ雄々しく立ち上がり!
ただただ勇気を鼓舞して駆け抜けろ!
第2楽章 葬送行進曲 アダージョ・アッサイ
「英雄の生前の活躍が偲ばれる」重々しくも打ち沈む感情が描かれます。
華々しい英雄の活躍があるということは、その裏返しとして戦士たちの死にも繋がっています。
時代を変えるべく戦った多くの勇敢な魂たちを慰めるべく厳かに展開する、名曲葬送行進曲です。
第3楽章 スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ
開放的でエネルギッシュなスケルツォ楽章です。
ベートーヴェンらしい力強さに満ちた楽章で、英雄の目覚ましい活躍が目の前で展開しますす。
第4楽章 フィナーレ:アレグロ・モルト
短めの序奏が鳴り響いた後に続いていく変奏曲たち。
主題としてはバレエ音楽《プロメテウスの創造物》のメロディが使用されています。
この主題を元にして、勇壮な巨大変奏曲が展開していきます。
英雄の活躍をありありと想像させる元気の出る楽曲に仕上がっています。
【名盤3選の感想と解説】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》

ヘルベルト・フォン・カラヤン:指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
【無料体験】 amazonミュージックUnlimitedで聴けます♫
アルパカのおすすめ度★★★★★
【名盤の解説】
カラヤンとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による1962年の録音。
- 切れるテンポ!
- ほとばしるエネルギー!!
- はじける情熱!!!
「芸術」と言えるまでに彫琢された…音…。
まさしく名指揮者カラヤンの最も脂の乗り切っていた頃の名盤。
ベートーヴェンの録音だけでも多くの録音を遺していますが、交響曲第3番《英雄》で限れば1962年盤の熱のこもった名盤がいいかも。
味わい深い晩年の録音ももちろん捨てがたいですが、エネルギッシュな面で1962年録音の名盤を選んでみました。
サー・ゲオルグ・ショルティ:指揮 シカゴ交響楽団
【無料体験】 amazonミュージックUnlimitedで聴けます♫
アルパカのおすすめ度★★★★☆
【名盤の解説】
カラヤンの名盤から感じられる切れの良さや弾むテンポ感には欠けるものの構築性のあるガッシリとした男性性の強い名盤です。
真の英雄が持つ包容力があって聴いていて安心感が感じられます。
流麗で美しく、また危なげないバランス感覚にも優れた万人にとって聴きやすい名盤とも言えそうです。
ブルーノ・ワルター:指揮 コロンビア交響楽団
【無料体験】 amazonミュージックUnlimitedで聴けます♫
アルパカのおすすめ度★★★★☆
【名盤の解説】
優美で温かい魅力を持った名盤です。
英雄のイメージと言えば、勇気があり力強いというものですが、こういった温厚さを伴った英雄も悪くないです。
ベートーヴェンが嫌ったのは、権威主義を持った英雄ですが、ブルーノ・ワルターの描く愛情のこもった英雄ならきっとベートーヴェンも受け入れてくれるはず。
パンチの効いた交響曲第3番《英雄》を好む方にはおすすめ出来ませんが古典派としての柔らかい美しさを堪能したい時にはグッと来る名盤です。
【まとめ】ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》

さて、ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》の解説とおすすめ名盤はいかがでしたか?
- 大いなる希望
- 燃える情熱!
- 讃歌、高らかなり!!
音楽家としては致命傷である「耳の病が悪化する」失意の頃のベートーヴェン。
劣悪な環境の中からでも美しい音楽を生み出し続けたベートーヴェンこそ「真の英雄」なのかも…?
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は、以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
関連記事↓