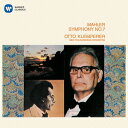「誰にだって寂しい夜はあるものです。そんな時には『共感してくれる人』がその寂しさを癒してくれるものです。」
されども、そんな人さえ、見当たらない時に、寄り添ってくれるのが音楽というもののありがたさですね。
この曲は、1905年に完成しているようです。
マーラーは1904年に、この曲で「夜の歌」と名付けられた第2楽章と第4楽章を作曲しました。
そして翌年の1905年に第1楽章と、3楽章、5楽章を作曲して、この第7番の交響曲の全てが完成したようですね。
そして、そののちには、この交響曲第7番全体を「夜の歌」と呼ぶようになったようです。
現代のこの曲に対する評価としては、「構成に難がある」とか「分裂症の傾向がある」などと言われてマーラーの交響曲の中では、マイナーな存在と言われています。
でも、アルパカとしては、実は、この曲がマーラーの交響曲の中では一番好きなのですよね。
マーラーには10曲の交響曲がありますが、どれも個性的で、しかも壮大。
そして、その壮大さはまるで、見上げた星空のひろがりのようで、「その音楽世界にただ息を飲むばかり」なのですね。
そんな交響曲の中でも、バランスがよくて(あくまでもアルパカの意見ですが…。)聴いていて心地いいのです。
とくに第2楽章と第4楽章の「夜の歌」が大好きで、「静かな夜を楽しむ」ときの癒しのBGMに、いいかも…。
今回のアルバムの紹介では、このうちの第4楽章について、書いてみたいなと思っています。
【解説】マーラー:交響曲第7番《夜の歌》
このような解説を見つけました。
2曲の「夜曲(ナハトムジーク)」は著しく特徴的だが、規模は割合小さく、控えめな存在である。それにもかかわらず、この2つの間奏楽章のお陰で、第7(交響曲)には「夜曲」とか、「夜の歌」の俗称があるのだ。第2楽章の「夜曲1」は、マイケル・ケネディによって、モーツァルト風な「月夜のロマンチシズムを20世紀の語法で再現したように見える」と評されている。マンドリンとギターが用いられている室内オケ的な第4楽章の「夜曲2」の方がノクターン風であり、愛の歌としての「小夜曲(セレナード)」風な性格をそなえている。
出典:志鳥栄八郎 著 「不滅の名曲はこのCDで」p164より引用
「悲劇的」をテーマに作曲された前作の第6番交響曲のあとの作品である第7番交響曲ですが、『悲劇の時を超えた先の穏やかさが顔をのぞかせる』そんな印象の曲です。
その穏やかさの象徴が第2楽章と第4楽章の「夜の歌」というわけです。
さて、では、この曲について書いていきますね。
【各楽章を解説】マーラー:交響曲第7番《夜の歌》
この曲は第1楽章から第5楽章までの5曲で成り立っています。
それでは、各楽章について解説したいと思います。
第1楽章:ラングサム(アレグロ)ーアレグロ・リゾルート、マ・ノン・トロッポ
(ゆるやかにー快活に、そして、決然と、しかしそれらを強調しすぎずに)
静かに始まる音楽は、まるで、「夜」のはじまりのよう。
だんだんと、いさましくなっていく音楽の中にも、どこかしら、「深まる夜」への序章のような響きを感じるのはアルパカだけなのでしょうか。
第2楽章:「夜の歌-Ⅰ」ーアレグロ・モデラート
(ほどよく速く)
少し楽天的なほっこりする内容です。
「夜の歌」のはじまり。つまり第1曲目ということで、いちにちが終わり、夕方の頃から時を追うごとに深まっていく様を描いているようにアルパカには聴こえます。
第3楽章:スケルツォ・シャッテンハフト
(影のように、流れるように、しかし速すぎずに)
すこ〜し、力強い感じですね。。
夜にもそん過ごし方があってもいいかも…ですね。
第4楽章:「夜の歌-Ⅱ」ーアンダンテ・アモローソ
(歩くくらいの速さで、 そして、かわいらしく)
こちらの「夜の歌」2曲目は、ますます深まりゆく「夜」という感じです。
そんな中で、人びとは、ロマンティックに過ごしたり、さらに、静かに、そして瞑想的に過ごすこともあることでしょう。
第5楽章:ロンド フィナーレ アレグロ オルディナーリオ
(ロンド形式で普通の快活さで)
「夜の歌」というよりは、希望に満ちた明日への賛歌という感じですね。
全編が、喜びを謳歌するような、明るい基調の曲といっていいと思います。
以上、簡単にこの曲のイメージを書いてみました。
【名盤解説】マーラー:交響曲第7番《夜の歌》
今回は、はじめに記したように、第4楽章の印象的な演奏というテーマで選んでみました。
レナード・バーンスタイン:指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック(1965年録音盤)
はじめに歌いだすソロヴァイオリンの音色の美しさに感嘆ですね。
その後は、ただただビロードのような夜のとばりが降りきて、舞台は完成。
その美しい夜のなかでは、まるで有名なロミオとジュリエットの物語が展開されるよう。
ひっそりやって来たロミオが歌いそのロミオの想いをジュリエットが受け取りながら、ただただ、静かに夜はふけてゆきますね。
そんなたくさんなメッセージの詰まった「夜の歌」です。
オットー・クレンペラー:指揮 フィルハーモニア管弦楽団
「ほお〜、ほお〜。」と鳴くフクロウと、
「ぷ〜、ぷ〜。」「ぴ〜、ぴ〜。」と
静かに 、静かに寝静まる鳥たちの寝息。
それをやさしく包むのは、暗い森をほのかに照らすまんまるの月。
それは深くて明るくて、とっても見事なこがね色。
やっぱり月は…月はやっぱり守り神。
鳥や木や、虫や草たち、スヤスヤと、眠りを守る、守り神。
今日もホントにありがとう。
夜を守って星月夜。
そんな静けさが、どこまでも深まる演奏が、このクレンペラー盤ですね。
「これだけ頑張っているのに、上司や先輩、同僚にすら理解してもらえない。」そんなときは、もしかしたら、自分が独りよがりになっていて、自分自身が「他の人たちの頑張りを受け入れ、認めていないというだけなのかもしれません。」
でも、そうは言っても、今、このひとときの満たされなさをどうすればいいだろう?
そんな時に聴きたい【寂しい夜に聴く癒やしの1曲】をご紹介しました。
【解説と名盤、まとめ】マーラー:交響曲第7番《夜の歌》
さて、マーラー:交響曲第7番「夜の歌」、名盤の紹介と解説はいかがでしたか?
マーラー:交響曲第7番「夜の歌」は、さまざまなひとの演奏を聴いてもさまざまな夜のあり方があるのだと、ただただ感心させられるのですよね。
みなさんは、どんな夜が好きで、どんな夜をすごしたいですか?
ぜひ想像してみてくださいね。
そんなわけで…
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
夜を静かに楽しみたいあなたへ…。