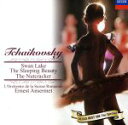優美な旋律♬
ファンタジックな物語!
めくるめくバレエ組曲!!
チャイコフスキーが作曲したバレエ組曲の中でも
- 白鳥の湖
- 眠れる森の美女
とともに「チャイコフスキーの三大バレエ」と言われる、チャイコフスキー :くるみ割り人形の解説とおすすめ名盤を紹介です。
- 【解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形
- 【あらすじを解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形
- 【各曲を解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形
- 【名盤を解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形
- 【解説と名盤、まとめ】チャイコフスキー :くるみ割り人形
【解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形

こんな解説があります。
ロシアのバレエは、19世紀後半に入ってめざましい興隆ぶりをみせた。バレエは、フランスの上流社会で好まれていて、それがやがて劇場で上映されて、一般の観客を楽しませることになった。ロシアでは、宮廷をはじめとする上流社会では、フランス文化が偏重され、教養としてフランス語を身につけていなければならなかった。そうしたことで、フランス風に華麗なバレエがロシアで流行をみたのも当然のことであり、長い冬に閉ざされた大都会の上流人士の重要な娯楽となった。
出典:門馬直美 著 「管弦楽・協奏曲名曲名盤100」Pp97より引用
チャイコフスキー :くるみ割り人形の原作はE・T・Aホフマンの「くるみ割り人形とねずみの王様」です。
1892年、チャイコススキーはペテルブルグのマリンスキー劇場の総監督からの依頼でこの曲を完成させました。
この輝かしいインスピレーションと完成度の高い一曲ができて、創作活動が充実していたチャイコフスキーです。
【あらすじを解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形

この物語は心優しい少女クララとくるみ割り人形との「夢」と「勇気」と「冒険」の楽しいファンタジーの物語ですね。
あらすじ
あるお城でのこと。
待望の王子の誕生に城内は大喜び。
城にいる老いも若きも、男も女も、身分の上下もこえて、みんな誰もが浮足立っています。
しかし、ある者が、そこにいたねずみの女王をあやまって踏みつけて殺してしまいます。
そのため、生まれた王子は呪われ、くるみ割り人形にされてしまったのでした。
クリスマス・イヴの夜、少女クララはドロッセルマイヤーおじいさんからくるみ割り人形をプレゼントされます。クララは大喜び。
しかし、それを見たいじわるなお兄さんは、そのくるみ割り人形を取り上げようとしてクララともめて壊してしまいます。
くるみ割り人形を不憫に思った優しいクララは枕元にそっと置いて布団をかけてあげて、眠りにつきました。
しばらくして、時計が0時を告げたとき、クララは夢をみます。
そして、気がつくと、自分の体がくるみ割り人形と同じ大きさになっていました。
ビックリしているのもつかの間、あたりを見渡していると、ねずみの軍隊が攻めてきているではありませんか。
そして、それに対抗するべく、おもちゃの兵隊たちが登場し、戦いをいどんでいきます。
戦いは平行線をたどりますが、クララの機転で、剣をつかみ、そして振りおろすことによって、ねずみの大将をたおします。
それを見たねずみの軍隊は、ほうほうの体(てい)で逃げていきました。
戦いがおわり、クララがふと気がつくと、くるみ割り人形は立派な王子の姿に変わっていたのです。
王子はお礼に、クララをお菓子の国へ案内します。
そこで、クララは、お菓子の精たちに歓迎されてパーティが展開します。
そして、王子とともに、楽しい時間を過ごしたのでした。
目がさめて、この出来ごとが夢であったことがわかります。
しかし、クララはこれが夢と思うことができずに、起こったことを実感をこめて、まわりの人たちに熱く語ってまわります。
でも、誰もかれもに、おざなりに聞き流され、がっかりするクララです。
その後、しばらくたったある日、突如として現れた、とある国の王子に求婚されます。
その王子は、たしかに、あのくるみ割り人形から姿を変えて出会った王子なのでした。
【各曲を解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形

小序曲
「夢がいっぱいの、少女クララの物語」その可愛らしさが曲全体に満ち満ちたワクワクしちゃう序曲です。
第1幕
第1場
- 1.情景
さあ、クリスマスパーティの準備です。
ささやくような弦楽器の歌から始まりますがだんだんとその曲調を強めながら期待と夢いっぱいなメロディで始まります。木管楽器の音の動きはロウソクの光のまたたきを暗示しています。ティンパニの強奏に続いて子供たちが客間に登場し,次の行進曲に移って行きます。
- 2.行進曲
子供たちがクリスマスツリーを囲んで、踊って回って踊ります。
管楽器で奏でられるファンファーレがあらわれます。
その後、弦楽器で奏でられるロディは、子供たちの弾む心と体を表します。
- 3.小さなギャロップ
弦楽器の歌う快速な曲から始まって、徐々に多くの楽器たちが絡み合いながら曲自体が駆けめぐります。
- 4.踊りの情景
子供たちにプレゼントを持って、ドロッセルマイヤーおじいさんがやってきます。
子供たちはワクワクしながら、目を輝かせてプレゼントを待ちます。
機械仕掛けの人形たちも踊ります。
- 5.情景
さあ消灯の時間です。
もう眠る時間が来たことを子供たちは知るのです。
ドロッセルマイヤーおじいさんはポケットからくるみ割り人形を取り出しますが子供たちはこぞって人形の取り合いが始まります。
そしてある男の子はくるみ割り人形を取り上げて壊してしまうのでした。
優しいクララは,くるみ割り人形用をベッドに寝かせてそっと布団をかけてあげます。
- 6.情景
時計が0時を指すとクララはくるみ割り人形と同じ背丈にまで縮みます。
「子どもたちの眠りの後から始まる、ファンタジーワールドの世界」。
そこへ誘われるクララの幻想的なイメージが音楽で展開します。
- 7.情景
ねずみの軍隊が、不穏な空気の中を攻めてくる感じが音楽で表現されます。
くるみ割り人形はクララのベッドから立ち上がり勇敢に戦いを挑みます。
くるみ割り人形が形勢の悪くなったところをクララの機転でねずみの王様にスリッパを投げつけます。
するとねずみ軍団は、ほうほうのていで撤退していきます。
そしてくるみ割り人形は勝利し、勇壮な曲調へと展開して第1場は終わっていきます。
第2場
- 8.情景 冬の松林
勝利の後の調和的な曲です。
王子とクララはお菓子の国へむけて旅立っていきます。
- 9.雪のかけらのワルツ
フルートが雪のかけらのハラリハラリと舞うさまを表現します。
ここで美しい合唱が表れて、第1幕の終わりを盛り上げていきます。
最後は再び、雪のかけらの舞う様が描かれて終わります。
第2幕
- 10.情景
やわらかい光と調和に満ちた音楽が展開します。
さあ、王子とクララは、いよいよお菓子の国へと到着します。
- 11.情景
王子とクララ金の舟に乗ってやってきます。
国をあげて大歓迎で2人を迎えます。
非常にチャイコフスキーらしい華やかな曲調の音楽です。 - 12.ディヴェルティスマン
ここからは、お菓子の世界のさまざまなお国柄を反映した民族的な曲が現れてきます。
a)チョコレート(スペインの踊り)
トランペットがボレロの曲調に乗って歌います。
b)コーヒー(アラビアの踊り)
静けさを表現した、しかし、エキゾチックな曲を展開します。
c)お茶(中国の踊り)
弾むように刻むファゴットとコントラバスの歌をフルートが優しいメロディで包み込みます。
弦楽器も弾むように奏されます。
d)トレパック(ロシアの踊り)
元気よく力強い1曲です。
ノリノリな曲調ので、どこまでも盛り上がり盛り上がりしながら展開する名曲です。
e)あし笛の踊り
ソフトバンクのCMでおなじみ…。
可愛らしく、優しい曲調の聴きやすく親しみやすい1曲です。
f)メール・シゴンニュとポリシネルたちの踊り
明朗でノリのいい音楽が現れます。
道化師が踊り狂う姿が描かれます。 - 13.花のワルツ
チャイコフスキー :くるみ割り人形の中でも、最も華やかで、きらびやかで、キラキラ光ってる音楽です。
むかしからCMでも多く取り上げられ続けていることからも、その素晴らしさがうかがえますね。
バレエとしても24名のバレリダンサーが華麗に舞います。
優雅で美しい、古今東西のワルツの中でもトップを争う1曲と言っても過言ではないでしょう。
メロディメーカー、チャイコフスキーの面目躍如!!
そんな1曲です。
- 14.パ・ド・ドゥ
a)アダージョ
この曲もチャイコフスキーらしい情感の深さが感じられる憂いを秘めた1曲です。
b)タランテラ
タランテラリズムで展開して、民族的な香りが漂います。
c)こんぺい糖の精の踊り
こんぺい糖の精の踊りです。
透明感のあるチェレスタが印象的な曲で、なんとも不思議な味わいをかもしています。 - d)コーダ
元気でアップテンポで、しかも流れるような麗しいメロディに乗って豪華なイメージで展開する感動的なコーダです。
- 15.終幕のワルツとアポテオーズ
壮大なワルツになります。
華々しく展開する全員が踊り、舞い上がるワルツです。
たくさんな感動を与えてくれた《くるみ割り人形》の最後を飾る壮大なイメージを持った素晴らしいフィナーレになります。
【名盤を解説】チャイコフスキー :くるみ割り人形

この「くるみ割り人形」には全曲盤や、抜粋盤がたくさん出ています。その中でも
カラヤン、ドラティ、ゲルギエフなど目移りしてしまうほどの指揮者がたくさんの演奏の録音を残していますよね。。
でも、そんな並みいる強豪の中から2つ選んでみますね。
アンドレ・プレヴィン:指揮 ロンドン交響楽団の「くるみ割り人形」
非常にスマートですっきりとまとまった心地よい「くるみ割り人形」です。
踊りのほうも足どり軽く、リズムもはずみます。
エルネスト・アンセルメ:指揮 スイス・ロマンド管弦楽団
「くるみ割り人形」物語のファンタジー性を骨太に情熱的に、そして、感性豊かに表現しています。
どっしりと力強い演奏です。
【解説と名盤、まとめ】チャイコフスキー :くるみ割り人形

さて、いかがでしたか。「くるみ割り人形」はかわいらしいおとぎ話の要素をふくんだ明るてかわいい組曲ですね。
「王子の復活とお姫さまの優しさ、ひたむきさ。」
こんな物語を音楽で感じてみるのもいいものです。
そんなわけで、
『ひとつの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
こんな音楽物語もいいですね。