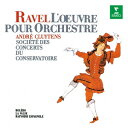雲間を舞台に舞う、踊る。
そんな華やかで、色あざやかな人びとに、心、合わせて舞い、踊ろうよ♬
- 【作曲までの出来事】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
- 【楽曲を解説】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
- 【8枚の名盤を解説】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
- 【解説と名盤、まとめ】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
【作曲までの出来事】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
今回は”オーケストラの魔術師”と呼ばれるモーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスという曲について書いていこうと思います。
こんな解説があります。
ラヴェルのオーケストラ曲といえば、「亡き王女のためのパヴァーヌ」や「ボレロ」といった作品が知られているが、そのほかにも多くの傑作を残している。これらの管弦楽曲はいずれも、”オーケストラの魔術師”とまでいわれたラヴェル独特の、華麗で色彩豊かなオーケストレーションが万全に発揮された音楽となっている。
モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスを作曲していた時期は、モーリス・ラヴェルにとって、失意の時期にあたります。
ちょうどこの頃、第一次世界大戦が勃発します。そのためモーリス・ラヴェルは従軍せざるを得なくなります。
担当は輸送兵、つまり戦場で様々な物資を運ぶのがお仕事です。
実際の戦いには参加しないものの、各地で人の死やそれにともなう悲惨な状況を見たことでしょう。それがもとで、モーリス・ラヴェルは肉体的にも精神的にも健康を害します。
そして、それに追い打ちをかけるように、非常に慕っていた母親を亡くすという不幸にも見舞われたようですね。
そんな「失意の数年」を過ごしたあとに、作曲されたのがこの「ラ・ヴァルス」です。
すっかり落ち込み、ふさぎ込んだ数年の後に、縮みきったバネが、力強くはね返すように「明るくて、華やかな1曲」が誕生!!
そんな1曲がモーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスと言っていいと思います。
「ラ・ヴァルス」とは英語で言うところの「ザ・ワルツ」つまり、「これぞ!ワルツ!!」とでもいう感じです。
でも、モーリス・ラヴェル自身は、尊大な(人をえらそうに見下すような)性格ではなかったので、いわば、ちゃんと訳すとすれば、「これぞ、フランスのワルツ」(本来、ワルツの本場はウィーンです)くらいの意味合いにとっていいのかもしれません。
まあ、いずれにしても、この曲が「ワルツ」の性格をもった明るくて華やかな1曲であるということには変わりはないですね。

【楽曲を解説】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
それでは、モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスの曲そのものについて解説したいと思います。
ラヴェルはこのモーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスについて次のような一文を書いています。
「渦巻く雲の切れ目から、ワルツを踊っている、たくさんのカップルが見え隠れします。
その雲がだんだん晴れてくると、くるくると回りながら踊っているたくさんの人たちでにぎわう、ひときわ大きなサロンが見えてきます。
その踊りのサロンは、だんだん明るくなっていき、シャンデリアの華やかな光が散乱し、音楽は響きわたる。
そう、それは、19世紀の王宮です。」
この文の流れと同じように、音楽は作られています。
つまり、「雲の切れ目に、ぼんやり見えてきた踊るカップル」のように静かに、そして、メロディラインもぼんやりとした感じに始まります。
すると、だんだんに「踊っているたくさんの人たちがはっきり見えて来る」ようにメロディラインがはっきりしていきます。
さらに、ワルツ特有の「ブンチャッチャ、ブンチャッチャ」というリズミカルな三拍子のメロディがハッキリと明確に奏でられていきます。
音楽が進むにしたがって、「シャンデリアの華やかな光が散乱し、音楽が響きわたる」ように展開し、盛り上がり、そして、終わっていきます。

【8枚の名盤を解説】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
では、そんな「華やかで楽しい」ウキウキする5枚の名盤を解説します。
アンドレ・クリュイタンス:指揮 パリ音楽院管弦楽団
ドイツ音楽も得意としたベルギー人のクリュイタンスですが、フランス人作曲家の音楽を演奏しても、フランス人以上にエスプリを効かせニクいばかりの粋な演奏を繰り広げます。
対象とする音楽によって、変幻自在に返信するマルチな音楽的資質を持った指揮者だったのでしょうね。
モーリス・ラヴェルを聴くなら一度は耳に触れておきたい1枚ですね。
シャルル・デュトワ:指揮 モントリオール交響楽団
う〜ん。
デュトワの華麗で優美な、このクセになりそなリズム感♫
たまりませんね!
どこまでも華麗でありながら、決して、コテコテの飾り立てた安っぽさは、ありません。
品のある、香り高さが魅力ですよね〜♫
この1枚で、ぜひ、あなたも「クセになって」くださいね。
エルネスト・アンセルメ:指揮 スイスロマンド管弦楽団
アンセルメもフランス音楽を得意としました。
骨太な音楽構築を行いながら、楽器ひとつひとつ、またいち音いち音がおしゃれなニュアンスをともなって発されます。
なんだかお酒を飲んでもいないのに、酔っ払って気持ちいい感じです。
レナード・バーンスタイン:指揮 フランス国立管弦楽団
いつも情熱的で熱い演奏を繰り広げるバーンスタイン。
そんなバーンスタインはモーリス・ラヴェルの音楽はイマイチ合わないのでは…。
ラヴェルの音楽は華やかでありながら、優美であってほしいですよね。
でも、なかなかどうして、このアルバムは「優美」なんですよ。
力強く熱いドライヴをするバーンスタインが指揮するは、フランス国立管弦楽団なのですから聴かせます。
バーンスタインの「熱」とフランス国立管弦楽団の「粋(いき)」がミックスされて素晴らしく心地いいサウンドが生まれていますよ〜。
ジャン・マルティノン:指揮 フランス国立管弦楽団
モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスは、華やかな1曲ですが、だからといって、あまりにも豪華絢爛(ごうかけんらん)に演奏しすぎるのはどうもしっくり来ない感じがするなあ。
そんな風に感じるのですよね。
それならば、ほどよく力強く、またほどよく繊細なこの1枚はいかがですか?
フランス生まれのマルティノンがフランスの作曲家、モーリス・ラヴェルの音楽をフランスのオーケストラを指揮してのフランス的エスプリ(知性)の効いた演奏…かな♬
雲の切れ目に浮かぶ踊る人たちの、モヤっとした表現からして、繊細に始まり、華やかに展開してからも、どこかしら品がある。
そんな演奏ですね。
冒頭で紹介したアルパカの経験のように、うつうつとした心のときに、スマホに入ってるこの名盤をポチれば、そっと寄り添ってくれて、元気もくれる。そんな名盤なのですよ♬
ピエール・ブーレーズ:指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
「『音の良さ』も考慮に入れたいな。」
そんなことを考えるなら、このブーレーズ指揮の洗練されつくした音に酔うのもアリですね。
”オーケストラの魔術師”と呼ばれたモーリス・ラヴェル作曲の「ラ・ヴァルス」を「現代の”音の魔術師集団”と言っていい、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」の演奏で聴く。
また、近現代の曲を演奏すると、それこそ魔術的な美しいアンサンブル(楽器同士の調和)で指揮するピエール・ブーレーズならではのモーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスを聴かせてくれます♬
グレン・グールド:ピアノ
モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスは、今回、解説した管弦楽版のほかにも、2台のピアノ用版と、ピアノ独奏版があります。
なのに、なのに…グレン・グールドは、何が気に入らなかったのか、あえて自分で編曲して、それをそのまま、録音したのですね。
グールドらしい破天荒な行ないにビックリですよね。
グールドらしい、「力強く、弾むようなタッチとヒラメキ!」
yuotubeでアップされた映像を見たらやっぱり、体も、弾んでました!!
こんな硬質な響きのモーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスもいいですね。
アレクサンドル・ギンジン:ピアノ
こちらもグレン・グールド風にギンジン自身のアレンジ版です。
すでに説明したとおり、ラヴェルの編曲版はちゃんと存在するのになぜ!?
そんなことを思ってしまいますが、ここはちょっと耳をかたむけてみましょうか。
グールドとはまた打って変わって華麗な弾きっぷりのピアノ版モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスが堪能できますね。
【解説と名盤、まとめ】モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス
さて、モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス、名盤の紹介と解説はいかがでしたか?
どうも最近、憂うつだし、クサクサして、気持ちが落ち込みがち。
そんな時は、モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルスのような華やかな音楽に耳をかたむけてみるというのもアリですよ。

そんなわけで…
『一つの曲で、
たくさんな、楽しみが満喫できる。
それが、クラシック音楽の、醍醐味ですよね。』
今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。